HSP看護師パパのポリラッチです🐭
現在、精神科病院で看護師として勤務し3人の子どもを子育て中で毎日慌ただしいです😅
HSPの特性として繊細さがあることだけでも大変ですが、看護師という緊張感と交代制勤務があり生活リズムが不規則で、さらに子育てで神経をつかい疲労困憊になります😅
しかし、まずはHSPを自己認識をすることで
『自分はこうゆう特性だからこう考えてしまうのかな』
『この疲れやすさはHSPの特性だからからかな』
と思考や行動も少しずつ変わってきます🌟
現在、HSP看護師の方でHSPの特性があることで夜勤のどこが大変なんだろう?と感じている方や
新卒として入職した方や最近転職し、これから『夜勤に入るけどHSPの特性で何に気を付けておかないといけないのか』など夜勤が不安な方にHSP看護師の夜勤の中でのしんどく感じる瞬間と対処法とメリットをHSP看護師パパの実体験と共にお伝えします
これから夜勤に入る方の心構えやこうすれば少しでもHSPの特性を活かせる部分とストレスを軽減できる方法をお伝えしていきます
HSPについて知りたい方はこちらからどうぞ
HSP看護師の夜勤のしんどい瞬間
- 夜勤前に入る前にも病棟の患者の状況が気になり家でも緊張感や不安感がある
過去に勤務していた病院で三交代制の時は深夜勤務の時は特に日中も仕事のことが気になり全然休めずしんどかった😅
対処法:二交代制勤務であれば、日勤と夜勤で仕事とプライベートの切り替えがしやすいのでHSPの特性として2交代制勤務の方が合う - 夜勤中、患者の睡眠中は静かであるが聴覚が敏感な為、ちょっとした物音にも反応してしまい疲れてしまう
対処法:仕事中で聴覚が敏感で疲れてしまうが、これに関しては特性としてメリットがあり、患者が中途覚醒しトイレ行動などで動こうとした時に気づき、すぐに訪室出来、患者の転倒・転落を事前に防ぐことが出来る - 夜勤の中で巡視中、色々な情報が入り気になり疲れる
巡視中、病室・廊下・ナースセンターなどの物品の配置や補充不足があると行わないと気が済まない為、夜勤中、動き回っていることが多い
メリット:巡視中の病室やトイレ・廊下などのコード類が出ている箇所や水濡れがあるとすぐに気付く事が出来るので、これに関しても転倒などを事前に防ぐ事が出来ている - 休憩中の仮眠中も患者や病棟内の物音を敏感に聞こえなかな仮眠が取れない
休憩中も仕事モードの時には聴覚は敏感で患者や病棟内の物音が聞こえてしまい仮眠が取れないことがある
対処難しい:仕事中で緊急の時などはすぐに対応する必要がある為、イヤホンや耳栓などで音を遮ることが出来ないので仕事中だという認識で対処することが難しいのが現実である
※病院によっては仮眠室が病棟の近くになく音などが聞こえにくい場合もあるので入職前の情報収集の一つとして情報を得るもの大切である - 夜勤帯でも患者の訴えや要求が多い
共感性が高いHSPの特性により患者から相談や訴えが多いことがあるが、それは夜勤の時も見られ日勤帯ではないと対応出来ないことも夜勤中に訴えらることがある
※前提として精神科病院で不眠・不穏・不安や身体症状の緊急性の場合は勤務帯関係なく対応している
対処法:患者からの相談や訴えに対しては傾聴し共感することが大切であるが、夜勤帯で対応出来ないことは患者に伝えることも大切になる
HSPの特性として共感性の高さや繊細さにより訴えに対して患者に断ることはかなり辛く、自分自身悲観的になってしまうかもしれないが、断ることの大切さも理解する
※精神科病院であり、患者の中には説明を正論で伝えても伝わらないこともあるので、患者の特性を理解し説明方法を考え伝える技術も精神看護では特に大切である
HSP看護師の特性を活かして落ち着いた夜勤にする
HSPの特性として共感性の高さや繊細さや五感の敏感さなどがあるが、夜勤帯は看護師の数は日勤帯と比較すると少ない為、看護師一人ひとりのスキルが求められます
HSPの特性を活かせば精神症状の面で特に患者を落ち着いて過ごし夜間の睡眠の確保に繋げることが出来ると思います
HSP看護師パパは夜勤中、緊張感をもち五感も敏感になり夜勤が終わった後は、どっと疲れが出ますが達成感ややりがいがあり仕事のモチベーションになっています🌟
HSP看護師として一般科病棟でも勤務した経験もありますが、精神科病棟の方がHSPの特性が活かせていると実感しています
HSP看護師でHSPの特性が強みになる職場についても投稿していますので下記の記事を参考にしてください
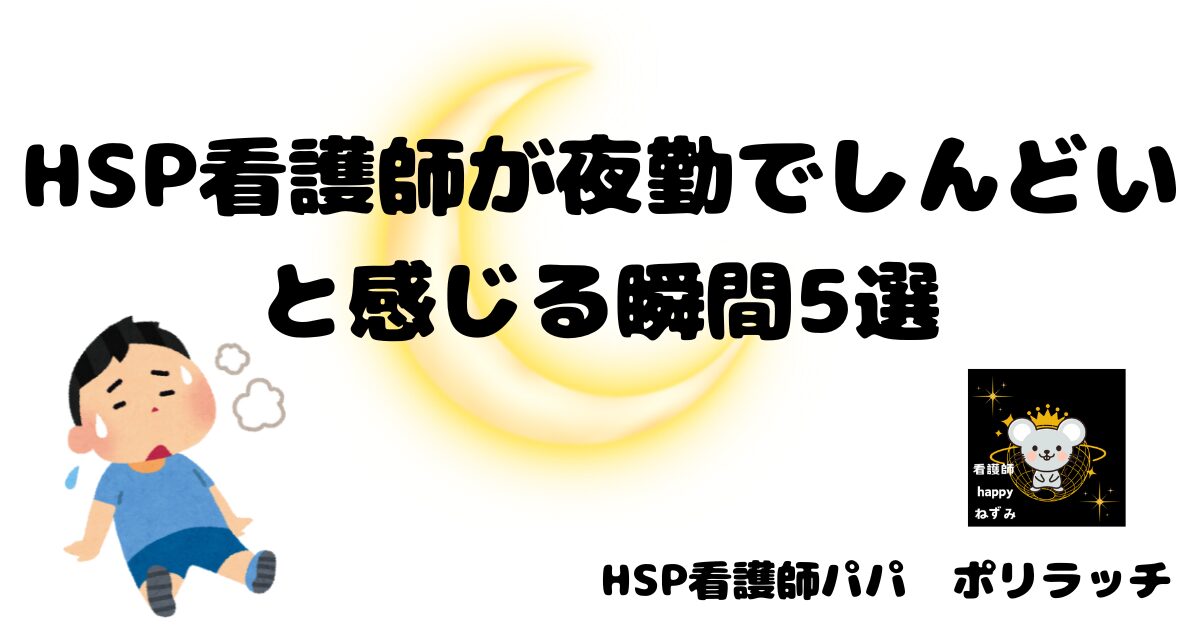

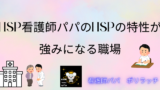
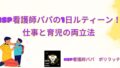

コメント